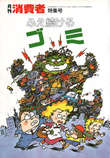増え続けるゴミ
|
出版年:1990年
出版社:日本消費者協会
定価:300円
月刊消費者 特集号
|
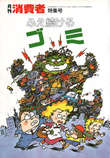
|
面白読本 大量浪費からリサイクル社会へ〜どうするゴミ問題
|
出版年:1991年
出版社:柘植書房
定価:1236円
|

|
PART 1
- ゴミの現状とその問題点
- 増え続けるゴミ
- ゴミにはどんな種類があるか
PART 2
PART 3
- 産業廃棄物はどうなっているか
- 産業廃棄物の種類と処理法
- 最終処分地がない
- 産業廃棄物にどう向き合うか
PART 4
- 市民が進めるリサイクル
- 20年間ゴミ問題と取り組んで
- 保谷市のゴミ行政を進める
- リサイクル条例の直接請求を進めて
PART 5
- わが国の静脈産業
- 静脈産業の歴史と問題点
- 紙・再生紙、 ビン、 ボロ、アルミカン・スチールカン他
PART 6
- 各地でのリサイクル活動
- 沼津市 「資源ゴミ」を回収して16年
- 町田市 リサイクル文化センターもできて
- 目黒区 住民手主導でリサイクルを実現
PART 7
PART 8
- ゴミ問題は地球環境保全の問題である
- 環境保全を前提にした企業活動を
- 地球を救うことは私たちが救われること
|
今、地球が危ない!
|
出版年:1992年
出版社:日本消費者協会
定価:300円
月刊消費者 特集号
|

|
地球環境読本
|
出版年:1995年
出版社:日本消費者協会
月刊消費者 特集号
1996年「新地球環境読本」に改定
|

|
新地球環境読本
|
出版年:1996年
出版社:日本消費者協会
|

|
第一章
第二章
第三章
>第四章
第五章
|
地球の未来はリサイクルできるの?
|
出版年:1996年(1997年改訂)
出版社:柘植書房新社
定価:1751円
|

|
第1章
- リオにでかけて見えてきたこと
- 国内だけでは解決できない
- 1992年リオの体験から
- 各国利害の妥協の産物が
- 地球市民の手でNGO条約を作る
- 資源小国・日本の過剰消費
第2章
- わが国リサイクルの現状と問題点
- 15才から再資源化業界に入る
- 回収したボロは製紙原料として
- とことん再利用する文化の中で
- 一升ビンはなぜ回収されなくなったか
- 市況に翻弄される鉄リサイクル
- アルミ缶のリサイクルは?
- 途上国の安い電力やODAを利用して
- アルミ缶再資源化の現状では
- 紙使用量は43年間で約23倍に
- 古紙暴落の原因はどこにあるのか
第3章
- なぜ輸入資源は安いのか
- ゴミ問題は実は資源問題なのだ
- 「カネ貸し」ODAが半分以上
- 資源を安く輸入するためのODA?
- IMFと世界銀行の役割とは
- 貧しい国をより貧しくする「構造調整」
- 私たちに何ができるのだろう
第4章
- 急速に枯渇している世界の資源
- 特に著しい熱帯林の消滅度
- 地球は物資循環により保たれている
- 化石燃料の可採年数は?
- 金属資源はあとどのくらいあるのか
- 27年間で消費は2.7倍に
- 地球物資循環のなかの分散と濃集
- 局地的に濃集してできる数々の鉱床
- 石炭と石油はどのようにできたか
- 肝心なのは消費の大削減だ
- 子供たちに続く世代への想像力を
第5章
- 環境先進国に見る永続可能な取り組み
- デンマークの環境・廃棄物政策
- 北の工業国はエネルギー消費を半分に
- この20年間に導入したシステム
- 原発推進研究所から大転換して
- デンマークの環境・廃棄物政策は
- 資源とゴミの両方に課税される
- オランダのNGOがつくりだした<「永続可能なオランダ」アクションプラン>
- 過剰消費削減のためのプログラムが
- 世界の誰もが同じ環境容量の権利を
- 木材資源の環境容量を具体例として
- どのような方法で消費削減を行うか
- このアクションプランの波及効果は
第6章
- 「永続可能な日本」の実現に向けて
- 循環型企業への実践
- 環境に最大の負荷を与えてきた事業活動
- 天然性素材から自動車の部品を
- 「もったいない」の哲学を事業に
- 分業から一環請け負いシステム
- ゴミ問題解決のために
- 資源小国日本には脱焼却しかない
- 第二処分場を多摩川水系の上流に
- ドイツの循環経済・廃棄物法とは
- 「容器包装リサイクル法」ができた
- 発生抑制こそ基本である
- 市民が進めるオルタナティブへの転換
- ゴミや環境をめぐる市民運動から
- 市民フォーラム2001が発足
- 自分たちで未来をひらく
|
新・デンマルク国の話€
−風が吹けば明かりがともるー
(講演まとめ)
|
出版年:1998年
出版社:北欧の福祉・文化研究会
定価:500円
|
持続可能な社会をめざす
|
出版年:2001年
出版社:柘植書房新社
定価:1785円
|

|
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
- 日本は、持続可能な社会に向けた法転換がなぜできないのか?
第7章
|
少しでも持続可能な社会を子供たちに手渡したくて
中村正子
ゴミ問題の案内書であり問題提起の書を
私が、『面白読本 どうするゴミ問題』を出したのは、まる10年前のことである。その後も、いくつものゴミやリサイクル関連の市民運動や取材を続けてきた。
今回出した『持続可能な社会をめざす』は、まず、ゴミ問題の案内書である。しかし、出てきてしまったゴミをめぐる問題だけを書こうとは思わなかった。できるだけ総合的に捉えなくては、解決策の見え方も違ってくるからである。したがって、第一章は「ゴミはもともと資源である」になった。
と同時に、この十年間に見聞してきたゴミをめぐる取り組み状況の変化と、十年たってもいっこうに変化しないものを整理し、問題提起をしたかった。
世は「リサイクル」時代となり、できる法律はリサイクル法ばかりである。しかし現在のわが国のように、大量生産・大量消費を転換せずして大量リサイクルを進めればどうなるだろうか?
第四章、第五章ではその結果を報告した。容器包装リサイクル法で、ゴミの六割を占めるといわれる使い捨て容器は本当に減ったのか。資源小国の日本ゆえに市場原理で機能してきた再生資源業界だが、余剰な供給のもと価格が下がる一方で、古紙や古繊維を筆頭に崩壊への一途をたどっている。
「大量な純資源輸入・消費」という蛇口を適度に閉めつつ、再生資源を循環させるための仕組みをつくらずして、どうしてリサイクルの輪がまわるだろうか。古紙や古布リサイクルの現状と問題点については第五章にまとめた。
わが国と環境先進国の法律の違いを
こうした現状を見るにつけ、「従来の法律ではだめだ。大量生産・大量消費を大きく転換し、排出されたゴミからでなく、川上の生産段階から変える法律でなくては」との思いが市民運動のなかで強くなっていった。そのためには、国を挙げて議論することが不可欠である。
1999年秋に出てきたのが、循環型社会形成推進基本法制定をめぐる動きであった。「官僚主導でなく政治の手で」という与党三党の実態はどのようなものだったのか。制定される過程で、市民運動側から政党に具体的に働きかけたものの一人として、ぜひ報告したいという思いが第六章になった。
国民の声をいっさい公聴することなく、政党間の妥協の産物としてできた日本の循環法とドイツやスウェーデンの法律との違いを見てほしい。
第七章では、大量生産システムからどのような仕組みに転換せねばならないのかという大まかな方向性を書いた。
17才を中心に子供たちへの批判があいつぎ、少年法の厳正化などが進んでいる。
しかし、子供たちの目前にあるのは、大人たちが生み出した温暖化問題からゴミ問題に至るまでの膨大な環境問題であり、社会的な規範の崩であり、ストレスや疎外感が増すばかりの持続不可能な社会なのだ。
ゴミ問題からその持続不可能生を知り、社会をいかに転換していくのかを考える一助になれたらというのが、私の願いである。
|
「著書紹介」へ戻る
表紙へ戻る
Copyright
(c) 2001-2004 中村正子 , All rights reserved.