デンマークの環境共生型エネルギーシステムに学ぶ
第2回自然エネルギー利用総合セミナー報告書
☆1973年エネルギー自給率1.5%から1997年エネルギー自給率100%達成へ
私がデンマークを訪問したのは、1997年6月のことだった。ケンジ・ステファン・スズキさんがユトランド半島北西部に開設した“風の学校"の第一期生としてでかけたのである。以前から、デンマークの環境政策を知れば知るほど、なんと合理的で納得のできるシステムなのだろうと多大な関心を持っていた。
風力発電の現場はもちろん、メーカーにも見学にでかけ、個人農場のバイオガス装置や共同バイオガスプラント、太陽熱利用の地域暖房、地域のコージェネレーション発電所、再生エネルギー研究所のフォルケセンターなども見学した。エネルギーだけでなく廃棄物政策にしても同じだが、デンマークでは「トクする方を選ぶと環境にいい」という総合的な経済誘導システムが実行されている。それは実に理にかなった仕組みなので「実行されて当然」だと思うものの、「無理が通れば道理が引っ込む」わが日本では、ほとんど実現されることがない。私は羨望の思いとともに、逆に、「デンマークではどうして、道理にかなったこうした政策をここまで推進できるのだろうか?」との疑問も抱いて帰国した。 環境問題に真っ向から向き合い、持続可能な社会への転換に向けて徹底した実践を重ねるデンマークの歩みへの共感と羨望、疑問は、帰国後もますますふくらんでいった。「デンマークは北海道の半分ほどの面積に人口約531万人が住む小さな国だからこそできるのだ」という声も聞こえるが、国の規模の違いができない理由とは思えない。
帰国してからデンマーク関連の数々の本を読み、何度も訪日されるステファン・スズキさんのお話しなどを聞いてきた。ここで、これまでのデンマークの風力発電を中心にしたエネルギー政策を確認するとともに、そうした政策を推進できる背景をも考えてみたい。 さて、私たちがでかけた1997年は、デンマークにとって記念すべき年だったのである。デンマークのエネルギー自給率が100%に達した年なのだ。1973年の第一次石油ショック当時、デンマークの一次エネルギー中の石油依存度は89%で、そのうちの90%以上は中近東から輸入していた。わが日本とほぼ同様のエネルギー内訳だったのである。しかし、それ以降、輸入石油からの大転換が、デンマークの最重要施策として取り組まれた。
すべての石油火力発電所を石炭火力に変え、エネルギー利用効率の高いコージェネレーション(熱と電気の併給)の普及に取り組んだ。地域暖房にはコージェネレーションを促進し、その割合は72年の29%から88年には55%まで向上した。75年には暖房検査制度を導入、エネルギー相談員が地域をまわり住居の点検や改善などをアドバイスして効果を上げた。住宅セクターの暖房用総エネルギー消費量が70年代から80年代にかけて、単位面積当たり45%も下がった。77年に建築法が厳しくなり、断熱が義務づけられた。79年から、風力・わら・木屑・バイオマス及び廃棄物を含む主要な再生可能エネルギーを利用した発電設備の建設費に補助金制度をつくった。また、77年にはエネルギー税システムを創設した。石油価格が下がった86年、デンマーク政府は石油価格を下げず差額分のエネルギー税率を引き上げ、省エネに大きな効果を上げた。
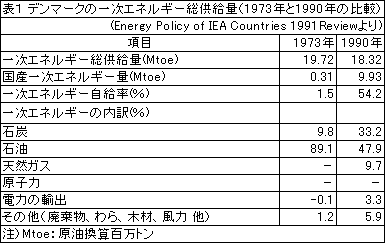
80年にはほぼゼロだった風力発電機の数は、91年末には3200基、42万キロワットに急増した。
こうして、右表1にあるように、デンマークの90年度一次エネルギー自給率は54.2%にまで上昇した。探査していた北海から天
然ガスや石油が出たのである。
一方、1990年の日本の場合は、相変わらず第一次エネルギーの85.4%を海外から輸入している。
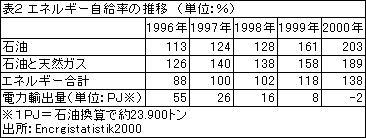 左の表2「エネルギー自給率の推移」を見てほしい。その後も増え続けたデンマークのエネルギー自給率は、1996年に88%になり、97年には100%に達し、98年からはエネルギーの輸出国になり、その量は年々伸びている。電力の輸出先は主にドイツ、ノルウェーだ。ノルウェーの電力供給は水力に依っているので、降水量が少なく電力が不足する時は不足分をデンマークが供給している。
左の表2「エネルギー自給率の推移」を見てほしい。その後も増え続けたデンマークのエネルギー自給率は、1996年に88%になり、97年には100%に達し、98年からはエネルギーの輸出国になり、その量は年々伸びている。電力の輸出先は主にドイツ、ノルウェーだ。ノルウェーの電力供給は水力に依っているので、降水量が少なく電力が不足する時は不足分をデンマークが供給している。
このデンマークでのエネルギー自給率の上昇は、北海油田からの石油と天然ガスの供給と、再生エネルギー源の開発・導入に力を入れてきたためである。
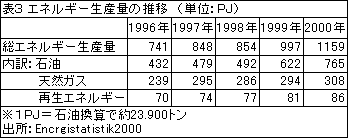 右表3には、96年から2000
年までのエネルギー生産量の推移がまとめてある。この推移によれば、デンマークでの再生エネルギーの生産量の伸びは毎年4PJとなり、石油換算で約96,000万トンの熱量となっている。
右表3には、96年から2000
年までのエネルギー生産量の推移がまとめてある。この推移によれば、デンマークでの再生エネルギーの生産量の伸びは毎年4PJとなり、石油換算で約96,000万トンの熱量となっている。
☆デンマークのエネルギー政策の歩みー目標達成のための具体的な方法を提示
前述した数々の施策は、1976年にデンマーク政府が発表した「EP76」、同1981年の「EP81」というエネルギー政策に基づいて取り組まれた。1985年、デンマーク議会はそれまで選択肢の一つに上がっていた原子力政策の取りやめを正式に決めている。
1990年には新政策「エネルギー2000」を発表した。目標は「2005年までに総エネルギー量を15%以上削減し、再生可能エネルギーを5%から10%に増やしながら二酸化炭素の排出量を20%削減する」「2030年には、デンマーク国内からの二酸化炭素の排出量を半減させ、再生可能エネルギーを全エネルギーの30%以上とする」などである。
この高い目標値を達成するための政策手段は次のようなものであった。省エネ、特に省電力の推進。エネルギー供給構造の変革、特にコージェネレーションの導入と拡大。再生可能エネルギーの導入など。さらに具体的に言えば、電気機器に対するエネルギーラべリングの導入、機器に対する最低エネルギー効率基準の導入、電気暖房を再生可能エネルギーと地域熱供給に転換する。炭素税などのグリーン税制の導入などである。
1995年末には、現状のままで推移したケースと省エネに最大限努力したケースについての2030年までのエネルギーを予測した政府報告「デンマークのエネルギー未来」が公表された。これをベースに翌96年に新エネルギー政策「エネルギー21」が発表されたのである。
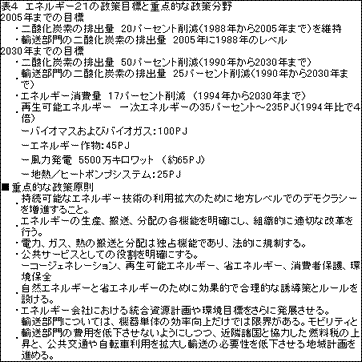 「エネルギー21」はEUの統合、国際環境の変化等を考慮しながら「エネルギー2000」の効果を検証、目標達成に必要な政策をさらに強化する内容である。(右表4参照)
「エネルギー21」はEUの統合、国際環境の変化等を考慮しながら「エネルギー2000」の効果を検証、目標達成に必要な政策をさらに強化する内容である。(右表4参照)
目標は2005年までに二酸化炭素の排出を20%削減との目標を維持、2030年までには二酸化炭素の排出量を50%に削減する。輸送部門の二酸化炭素排出量の25%削減(1990年から2030年まで)。同じく2030年までの目標には、エネルギー消費量を17%削減する(1994年から2030年まで)ことや再生可能エネルギーを一次エネルギーの35%にすることが上がっている。
再生可能エネルギーの内訳は、バイオマス及びバイオガス、風力発電、エネルギー作物、地熱/ヒートポンプシステムである。
それらの目標を進めるのは、大幅な省エネルギーと大幅な自然エネルギーの導入である。「再生可能エネルギー」「省エネルギー・エネルギー効率化」「輸送部門」のうち前二課題の内容を紹介したい。
「再生可能エネルギー」
〈バイオマスによるコージェネレーションの推進〉
・ 2005年までにすべての廃棄物埋立場からのバイオガス利用。
・ 新たな天然ガス導入はできるだけバイオマスに転換。
・ エネルギー作物(菜種など)の実証開発プログラム。
〈風力発電〉
・ 洋上風力発電の推進。2008年までに75万キロワット、2030年までに400万キロワット。
・ 家庭用風力発電(熱・電力両用)の推進。
・ 風力発電の計画を一般の地域計画に統合。
〈太陽熱利用の推進〉
〈地熱利用の推進〉
〈自然エネルギーアイランド〉
・ 地域が主体となって、自然エネルギーシステムへの大胆な社会的実験を行う。
〈地域イニシアティブの推進〉
・ ローカルアジェンダ21の活動に関連しつつ、地方における行政、政治、エネルギー会社、環境事務所、環境NGOなどによる協力関係を拡大する。
「省エネルギー・エネルギー効率化」
〈セクターをまたがる政策手段の開発〉
・ 省電力トラストの設立。(1キロワット時あたり0.6エーレの徴収)
・ 建築物の省エネ節水向上法の導入。
・ 建築基準の改定。
・ 既存の建築物の改善。
・ 情報活動の再組織化。地域ベースの活動の強化。「持続可能な発展と自然エネルギー委員会」の設立。
・ 製品対象の省エネルギー努力。エネルギーラベリングの強化、拡大。(自転車に広げる)自主的な協力によるエネルギーラベリングの拡大。エネルギー低効率の機器の排除。エネルギー高効率の機器の優先購入。
〈炭素税などのグリーン税制の強化〉
・ アグリーメントを通じた産業界からの二酸化炭素の削減。
〈研究開発〉
☆洋上風力発電が増え、風力発電だけで二酸化炭素削減目標値の約40%をすでに削減
では、実際に自然エネルギーはどのように推進されているのだろうか。
「エネルギー21」では、2005年までに150万キロワットの風力発電の導入を目標としているが、これは1999年に達成している。これで33億キロワット時の電力を生み出し、二酸化炭素削減の目標である5860万トンの四分一にあたる二酸化炭素を削減したことになる。 2001年6月末のデンマークの風力発電設備は約6400基あり、約238万キロワットを発電している。これにより、電力消費量の約16%に相当する59億キロワット時をまかなっているのである。
こうして、デンマークでは陸上の風力発電装置の設置場所が限られてきたので、前述したように、政府は洋上ウィンドファームの建設計画を作成したのである。すでに1991年にデンマーク初の洋上ファームがVindebyに建設(陸からの距離2 、450KW×11基)され、95年に500KW×10基(同5 )、2001年には2MW×20基(同3 )のウィンドファームができ、稼働している。
この2MW×20基の設備を持つ現在世界最大の洋上ウィンドファームは、コペンハーゲン港のわずか3キロ沖にある。年間見込み発電量は9000キロワット時で、それによりコペンハーゲン市の電力消費量の3%がまかなえて、それは一般住宅約2万5000戸分に相当する。この総設備投資額は3億5000万クローネ(約53億円)であった。この洋上ウィンドファームは協同組合の風力発電としても世界最大である。ウィンドファームの半分を8552人が出資した協同組合が所有し、残り半分をコペンハーゲンエネルギー会社が所有している。協同組合における出資者の負担額は、1口当たり4250クローネ(約64000円)で、ほとんどの出資者は4〜5口を所有している。
またユトランド半島では電力会社の共同事業体が、2MW×80基(同14 )のウィンドファームを2002年稼働をめざして建設中である。年間見込み発電量は約6億キロワット時との予想で、これは一般家庭15万戸分の電力である。
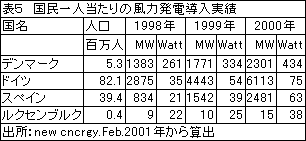 この洋上ウィンドファームの建設では、国際入札が実施されたが、デンマークのベスタス社が落札した。2003年完成予定の2.2MW×72基(同10 )については入札が終わっている。デンマークでは洋上ウィンドファームを建設するために2MW〜5MWクラスの大型風力発電機の開発が要求されている。
この洋上ウィンドファームの建設では、国際入札が実施されたが、デンマークのベスタス社が落札した。2003年完成予定の2.2MW×72基(同10 )については入札が終わっている。デンマークでは洋上ウィンドファームを建設するために2MW〜5MWクラスの大型風力発電機の開発が要求されている。
大規模なこれらウィンドファームにより発電量は飛躍的に増えていくだろう。しかし、左表5にあるように、すでに2000年末での一人当たり風力発電導入実績ではデンマークが断然多く、約434ワットとなっている。
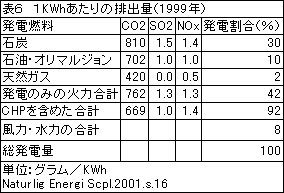 デンマークが風力発電の導入を促進している理由の一つに、環境汚染物質の排出削減がある。それぞれの発電方式ではどれくらいの環境汚染物質を排出しているのかが左表6である。例えば、デンマークにおける発電量の約30%を占める石炭火力発電の場合は、キロワット時当たり二酸化炭素810グラム、二酸化硫黄1.5グラム、窒素酸化物1.4グラムを排出している。
デンマークが風力発電の導入を促進している理由の一つに、環境汚染物質の排出削減がある。それぞれの発電方式ではどれくらいの環境汚染物質を排出しているのかが左表6である。例えば、デンマークにおける発電量の約30%を占める石炭火力発電の場合は、キロワット時当たり二酸化炭素810グラム、二酸化硫黄1.5グラム、窒素酸化物1.4グラムを排出している。
それでは、風力発電を導入することで、環境汚染物質の排出をどれだけ削減できるのだろうか。
表7は風力発電機の定格出力別の二酸化炭素排出削減量である。ここでは、風力発電機は定格出力1キロワット当たり年間 2300キロワット時を発電し、最新型の石炭火力発電では1キロワットを発電するために平均795グラムの二酸化炭素を排出すると仮定されている。
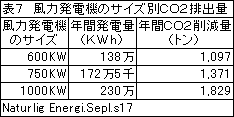 デンマークのエネルギー製作では、2005年に二酸化炭素を1988年レベルから20%減
少させること、つまり、1200万トンを削減 することを目標としている。現在、風力発電により約59億キロワット時が発電されているので、二酸化炭素の削減量は約470万トンとなり、政府目標の約40%がすでに削減されている。
デンマークのエネルギー製作では、2005年に二酸化炭素を1988年レベルから20%減
少させること、つまり、1200万トンを削減 することを目標としている。現在、風力発電により約59億キロワット時が発電されているので、二酸化炭素の削減量は約470万トンとなり、政府目標の約40%がすでに削減されている。
☆発電コストに外部費用を含めたEU総合開発局の調査では、風力発電が最も安い
このように再生可能エネルギー源による電力供給が毎年増えているため、2002年に入ってから、デンマークの電気料金の徴収方法が変わった。
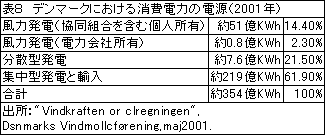 デンマークの年間電気消費量
約354億キロワット時は、左表8 にあるように、風力発電・分散 型発電・集中型発電から供給されている。デンマーク政府はすべての電力消費者に対し、その
中で風力発電と分散型発電による電力を優先して購入すること を義務づけたのである。(電力会社が所有する風力発電を除く) デンマークの電力供給体制は、ユトランド半島とフュン島を管理するEltra社と、シェーランド島とその近隣の島々を管理するElkraft社の2社に分かれている。Eltra社の領域内には風力
デンマークの年間電気消費量
約354億キロワット時は、左表8 にあるように、風力発電・分散 型発電・集中型発電から供給されている。デンマーク政府はすべての電力消費者に対し、その
中で風力発電と分散型発電による電力を優先して購入すること を義務づけたのである。(電力会社が所有する風力発電を除く) デンマークの電力供給体制は、ユトランド半島とフュン島を管理するEltra社と、シェーランド島とその近隣の島々を管理するElkraft社の2社に分かれている。Eltra社の領域内には風力
発電と分散型発電が多いことから、消費電力の46.3%(2001年)をそこから購入する義務が消費者に課された。
また、Elkraft社の領域内の消費者には、22.8%の電力購入義務が課された。送電力消費量から購入義務のある電力量を引いた残りの電力は集中型発電から購入されることになった。
また、これらの政策で風力発電の発電原価が高い分については、政府が約20億5000万クローネ(約38億円、2001年)の補助を出すことになった。
ヨーロッパやデンマークにおいても、風力発電は発電コストが高いと思われているが、EUの総合開発局の調査では、風力発電は発電コストが最も安いという。というのは、次のような外部費用(発電することで引き起こされる地球温暖化、環境汚染、国民健康の悪化などに対処するためにかかる費用)が風力発電は他の発電方式とくらべかなり低いからである。デンマークでの石炭火力発電の外部費用は風力発電の40〜70倍である。調査報告書によれば、EU諸国の発電の外部費用は国民保健の支出額だけで、EU内の国民総生産の1〜2%にあたる6300億〜1兆2600億クローネだという。アメリカでも、1973年から炭鉱労働者が塵肺で2000名死亡し、そのために350
億ドルの保証金が支払われたと言われる。発電コストを考える時には、この外部費用も含めて考えることが必要なのである。
☆デンマークの環境政策に大きな影響を与えたのは国民高等学校であった
デンマークで環境産業が発展してきた背景には、前述した国民の大きな力がある。特にパイオニアの役目を果たしてきたのがフォルケホイスコーレ(国民高等学校と訳されている)の存在だ。
この国民高等学校とは、デンマークで150年ほど前から始まった自由な学校である。その言葉は「民衆(国民)の大学」を意味する。現在、デンマーク全国で約100校を数え、また、世界にも広がっている。17歳半以上なら誰でも学ぶことができるが、試験を拒否し、資格も与えず、全寮制で教師と学生が共同生活をして学び、カリキュラムは自由で、助成金は受けていても国家の干渉を受けない私立の学校だ。
この学校は近代デンマーク精神の父であるN.F.S.グルントヴィによって構想された。その自由と人間解放をめざす精神ゆえに「生のための学校」とも言われ、今日のデンマークを築く原動力になった。フォルケホイスコーレの存在は学校教育にも大きな影響を及ぼしている。9〜10年の義務教育期間中もほとんど試験はなく、お互いの話しあいを土台に授業が展開される。自由に何ごとにもチャレンジするデンマーク人の行動力は、こうした背景や教育などから育まれているようだ。
アスコウ・ホイスコーレの教師となったポール・ラ・クールは、1891年から風力発電の開発に取り組んだ、デンマーク風力発電研究の元祖である。
また、学校の電力供給用として教師と生徒が一緒になって小型風車を製造した国民高等学校がたくさんある。特に、1978年に2MWのダウヌィンド型風力発電機を開発したTvind国民高等学校は有名だ。現在、世界最大の風力発電機メーカーに成長したVestas社の前身は農耕器具メーカーで、風力発電機開発当初の1977年頃には知識を持つエンジニアが一人もおらず、Tvindの風力発電機を開発した関係者を含め、多くの市民の協力を受けている。 市民の力で始められたのは、風力発電機だけではない。現在、デンマーク自然エネルギーの二番手として期待されているバイオガスプラントも、ごく普通の農民が始めたのである。何人もの農民が失敗を重ねながら努力したのである。これらの人々はエンジニアだったわけではないが、環境産業に大きな役割を果たしてきた。
また、デンマークが原子力を選択肢に入れながらもそれを選ばす、クリーンな再生可能エネルギーを推進したのも、環境NGOの多大な働きがあったからである。
第一次石油ショック後、デンマーク政府が原子力発電所の建設を公約した直後の1974年1月、NGOの「原子力発電情報組織(OOA)」ができた。OOAは実質的には国内唯一の反原発組織で、政府が原子力発電の推進を始める頃には、すでにキャンペーンを行っていた。「原子力反対」と掲げるキャンペーンではなく、「エネルギー政策を民衆が決める権利」を全面に打ち出したのである。「国民への情報提供組織」として全国130ヵ所に広がる草の根組織であると同時に、少数の戦略家で構成される本部事務局が政府や議会、電力会社への対応を一手に引き受けた。
同じく74年春、政府は原発のキャンペーンのために「原子力情報委員会」を設置、デンマーク教育にたずさわるさまざまな有識者が任命され、委員長にはフォルケホイスコーレの全国組織代表が指名された。当時、エネルギー政策を所管していた産業大臣もフォルケホイスコーレの出身であった。委員長は事務局長に、巨大技術や軍事技術に批判的な言論活動を展開していたゲールツェン氏を指名。以降、75年までに6冊のブックレットを出した。ブックレットは賛成と反対を対比的に構成、最後には「代替エネルギー」を出版している。こうした活動はOOAや市民には支持されたが、政府は嫌がり、76年に委員会を閉じてしまう。しかし、その間のOOAの原発モラトリアムの要求は政治的な支持を得ることに成功し、原子力計画は一年間延期され、76年春には「原発法」が議会を通過したが、OOAは約80万部の新聞をデンマーク中に配布し、法律の施行を止める署名を6週間で17万人分集めた。
政府が76年に発表した、15基の原発で拡大するエネルギー需要をまかなおうという総合エネルギー政策「EP76」に対し、OOAと若い科学者たちは「AE76」という代替エネルギーシナリオを作成して出版し、国民の支持を得た。78年には原発の候補地からコペンハーゲン、オーフスなどの大都市に向け5万人以上の参加者が2日間にわたるデモ行進を行った。それ以降もさまざまな政治的活動を続け、チェリノブイリ原発事故の一年前の1985年、デンマーク議会は原子力計画の放棄を決めたのである。NGOと国民の努力の結果であった。 デンマークの先進的なエネルギー政策を推進させてきたのは、反対するだけでなく、常に対案を提起して活動してきたねばり強いデンマーク市民・NGOの活動であったことを改めて強く思う。と同時に、「この日本を変えていくために、私たちはどう諦めず柔軟にしたたかに活動するのか」と問われてもいるのである。
昨2001年11月20日にデンマークで行われた国会議員、市町村議員、県議会議員の同時選挙の投票率は87%であった。この結果、社会民主党と社会自由党の連立政権は敗れ、穏健自由党とデンマーク国民党が大勝し、穏健自由党と保守党の連立政権に変わった。2002年1月29日、新内閣は政策大網を発表した。大網には、所得税と不動産税の増税停止、病院の治療待ちリストの軽減、育児家庭と高齢者に対する補助の改善など、約70億クローネにのぼる政策の変更を打ち出した。
この変更により、再生エネルギー分野の補助予算1億5000万クローネが全額削除された。再生可能エネルギーの普及を担ってきたフォルケセンターも、2001年に800万クローネだった政府補助が全額削減され、22人のスタッフのうち15人も解雇せねばならなくなった。洋上ファーム計画についても、入札が終わった2カ所を除き、会社に建設義務を課さないと発表している。また、再生可能エネルギーの利用とその他のエネルギー経済プロジェクトへの補助金なども全額削除された。
これ以外の削減項目は、環境援助・途上国援助、中央・地方公務員の新規採用制限と効率化、103の協議会・委員会の補助金打ち切りや合併などである。
これにより、デンマークが進めてきた大規模な洋上ウィンドファームの建設にもブレーキがかかる見込みである。
「水と空気を守る」環境エネルギー政策により国民の健康管理や地球温暖化防止に努め、その中でデンマークの環境産業を育て雇用を確保してきたデンマークは、今後どう変わっていくのだろうか。新内閣が発足して半年以上がたつが、これらの政策変更に対する批判が国内外から聞こえているそうだ。
EUでも有数の環境研究NGOであるフォルケセンターでは、22人のスタッフがたった7人に激減したという。これまで非常にお世話になってきたメゴード所長をはじめとする同センターの今後が大変気にかかる。
「地球の未来はリサイクルできるの?」(中村正子著 つげ書房新社)ほか。